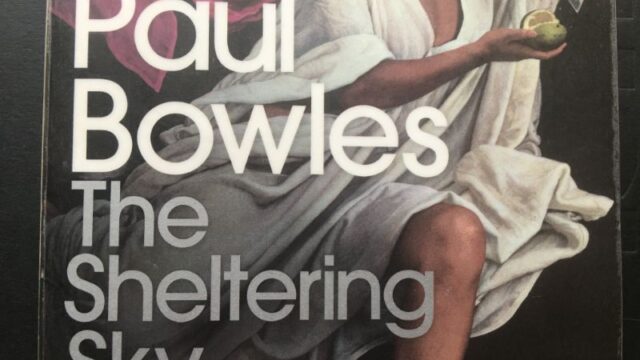アンソニー・ホプキンス主演の英国映画、「ハワーズエンド」を見ていて、ヴェネツィアの家にあったのとおなじ椅子が出てきて息をのんだ。赤いアラベスク模様の、ダマスク織りの布の椅子。ヴェネツィアの絹織物の老舗、ルベッリの椅子だ(と思う)。
それはもともと義父母の家の客間にあった。長椅子とシングルの椅子がふたつ、ヴェネツィアン大理石の床の上に置かれていた。両親が日本から初めて来たとき迎えてくれたのがこの客間だった。
その後結婚して夫が家の一角をもらい、客間はそのまま居間になった。アンティークだから大切に使わなきゃと思ったのは最初だけ。そのうち遠慮がなくなり、昼寝したり、子どもがぴょんぴょん跳ねたり、ずいぶん荒く使ってしまったっけ。
その見慣れた赤いアラベスクが、ロンドン郊外の緑に囲まれた屋敷、ハワーズエンドの書斎にあった。屋敷の主人であるアンソニー・ホプキンス演じる主人公がその赤い椅子にすわり、息子たちに説教をしている。亡き妻はこよなく愛した館と庭を、息子たちでなく、ひとりの友人女性に残すと遺言した。その遺言は家族に激震を起こし、館の相続をめぐって数々のドラマが起こるというストーリーである。
ルベッリ(Rubelli)は1781年、ヴェネツィアン・シルクの店として創業。1902年にはサヴォイア家のマルゲリータ女王から発注を受け、1922年にはローマやフィレンツェなどイタリアの主要都市に店をかまえる。ダマスコ織り、ベルベット、どれもうつくしい光沢と重厚な色が特徴で、この映画は1910年代を舞台にしているから、その時代のテイストを表わすのにルベッリの椅子を使ったのかなと思う。
赤いアラベスクを見たとたん、英国の緑の館のお話が吹っ飛び、ヴェネツィアの日々に心が飛んだ。夫が子どもを肩車している姿。義父母の笑顔。いくつもの誕生日、復活祭、カーニバル。夏の日の運河のきらめき。冬の窓ガラスを曇らせる白い霧……。
その日に帰りたいわけではない。なつかしいというのともちがう。ただ、確実にあった日常、存在していた人々が今はいない。そのことが信じられない。こんなにありありと覚えているにもかかわらず……。ほんの数秒、画面に映っただけの赤い椅子。それに心を乱される。
長いこと、物は物でしかないと思っていた。物なんかにかまってないで前に進まなくてはと。離婚して帰国した際もスーツケースひとつで帰ったし、引越しのときなどもあまりためらわず物を捨てた。だから今の生活には今の物しかない。
考えてみたら、それは自分なりの方便だったのだろう。過去に引っ張られないよう、目の前のレースに集中するため、競走馬が遮眼革を嵌めるように昔の物を排除した。
が、気がついたら子どもは独り立ちし、自分も還暦を迎えた。もうそんなにしゃかりきになって前を向く必要もない。映画でルベッリの椅子に出くわし、心は揺れたが、それを追いやる必要はもうなかった。あの時間も、今の時間も、現在の自分のなかに共在している……そのふしぎさにただ思い入った。
そして、あらためて物の力を思い知った。あの椅子を見て、一万kmの距離、何十年の時間をいっきに飛んだ。
これまで記憶力には自信があったので、物はなくても覚えていられると思っていた。が、目に触れないものはやはり遠くなっていく……。
これから記憶力が衰えていくことを思うと、もっと物を取っておけばよかったとちょっと悔やまれる。が、これでよかったのかもしれないとも思う。目に触れないから、忘れていられたから、心乱されずにすんだ。忘れるということは神さまの思いやりかもしれないのだ。
映画で、ハワーズエンドの屋敷と敷地は、やはりこの人しかありえないという人の手にわたる。そして当初想像もできなかった人がそこで暮らすことになる。
アンソニー・ホプキンスがすわっていた赤い椅子。あの椅子に、今度はだれがすわるのだろう?
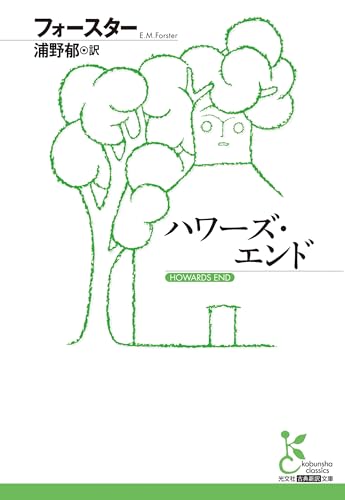
ハワーズ・エンド (光文社古典新訳文庫 K-Aフ 15-2)
★最後までありがとうございました。ブログランキングに参加しています。よかったら応援クリックしていただけるとうれしいです。
![]()
にほんブログ村
UnsplashのMathias Redingが撮影した写真, Thank you!