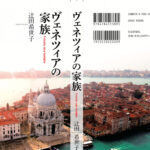ふとハノイに行ってきた。夏休みどこか行きたいねと娘と言っていたが、おたがい忙しく計画も立てられないまま夏も終わり、あきらめていたのが、遅めの休みが取れてぎりぎりになってハノイに決めた。
わたしも娘もベトナムは初めてだ。わたしは二十代のころ行こうとしたがビザを取るのが億劫でやめ、その後機会がなかった。
日本から飛行機でたった5時間余。あたりまえだがヨーロッパに比べると断然近い。これまで三十年近くイタリアと日本を行ったり来たりしてきたあのフライトの長さを思うと雲泥の差だ。近いっていいな、楽だなぁというのが、三十年ぶりにアジアに旅した最初の感想だ。
空港に着くとタクシーの運転手さんたちの呼び声にもみくちゃにされる。想定内だが夜遅かったこともあり、ちょっとこわかった。が、めげずに、教わってきた通りgrabというアプリでタクシーを呼び市内へと向かう。
高速を抜け、市内に入ると、車窓から夜の街が見えてきた。夜店みたいなものが出ていて街のにぎわいが伝わってくる。
びっくりしたのがバイクだ。絶え間なくクラクションを鳴らしながら、信号も無視、ノーヘル、サンダルばきで、ふたり乗りどころか、赤ちゃん、幼児ふたりをはさんで一家四人、五人で乗っている。それで車やトラックの間を平気ですり抜けていく。無法というか、野生というのか、見ているこちらのほうが冷や汗たらたらだが、本人たちは涼しい顔だ。
その夜は早々に寝て、翌朝、町歩きにくり出した。
朝の光のなかで見る旧市街はあざやかな色に満ちていて、まるでお祭りのようだ。街路をはさんで両側の建物から、赤地に黄色の星が描かれたベトナムの国旗が無数につるされ、はためいている。わたしたちが訪れたのは9月後半だったが、9月2日がベトナムの建国記念日であったからその名残だったのかもしれない。
もう9月も後半だから少しは涼しくなっているかもというささやかな期待は見事にはずれ、最高気温は35度を超え、ぐったりするほど蒸し暑い。
歩き出してみると、歩道は実質バイクの駐車場になってしまっていることがわかった。ぎっしりバイクが停められていて歩けない。また、飲食店の前では小さなプラスチックの椅子がいくつも置かれ、客が飲食している。よって歩行者は、停めてあるバイクや飲食している人たちの合間をすり抜けたり、それも不可能な場合は(不可能なことが多い)車道に出たりをくり返しながら歩くこととなる。
信号はあるがほぼ守られていない。車もバイクも好き勝手やっている印象。そのため道を渡るのにひと苦労。右を見て左を見て耳を澄まし、車とバイクが切れた瞬間を目ざとく見つけて渡る。
スマホで地図を見つつ、ひっきりなしにクラクションを鳴らされながら四方八方に神経を張り巡らせて歩くので、初日はぐったり疲れた。このクラクション、挨拶なのか、鼻歌がわりなのか、とにかく途切れることがない。
それでも初めて訪れる国がもの珍しく、きょろきょろしているうちにずいぶんな距離を歩いた。
旧市街は雰囲気のある古い町並みで、商売ごとの通りに分かれている。カゴ・ゴザ通り、仏像・ハンコ屋通り、シルク通り、漢方通りといった具合だ。でもそこで現代生活が営まれていて活気にあふれる街を、バイク、車、人がごっちゃまぜになって通っている。伝統的な円錐型のベトナムの麦わら帽子をかぶり、荷車にマンゴーやココナツ、ドラゴンフルーツといった果物を乗せて歩いている行商人もよく見かけた。伝統と現代が融合している感じ。
町の憩いどころ、ホアンキエム湖では、若い女性たちがセルフィーを撮りまくっている。なかにはアオザイを着て、ハスの花の花束など小道具、レフ板まで用意してきて友達どうしで撮りあっている子たちもいる。すごいなぁ、みんな写真が好きなのね。
あきれているその隣で、うちの娘も負けじとセルフィーを撮っている。そんなに撮ってどうするの?と聞くと、インスタに上げたり、友人たちに見せて楽しむのだそう。若いデジタル世代は旅をするにもリアルとヴァーチャルと両方で楽しむんだな。
一日だけハノイを離れ、ハロン湾クルーズに行った。そのときはツアーでベトナム人のガイドさんが付いたのでいろんなことを教えてもらった。
ベトナム人ひとりにつき一台はバイクを持っていて、そのほとんどがホンダだとか。ベトナムの家の入り口が横に狭いのは広くすると値段が上がるから、でも奥は深いうなぎの寝床スタイルであるとか。ベトナム戦争の枯葉剤が原因で障害を持って生まれた人が多いが、その人たちの多くは刺繍の仕事に従事して社会参加している。ベトちゃん・ドクちゃんの弟、ドクちゃんは結婚して双子の父となり、大阪で日本とベトナムの友好のために活動していることも。
なかでもベトナムの歴史について教えてくれ、誇らしげに言った言葉が忘れられない。「ベトナムはアメリカに負けなかった唯一の国です」。「中国もフランスもアメリカもベトナムを欲しがった。戦争をしている時代が長かったけど、1976年に南北統一を成し遂げて独立した」
ベトナム建国の父、ホーチミンがベトナム人に大変敬愛されているのは、わたしのような一観光客にも感じ取れた。お札はすべてホーチミンさんのお顔だし、お店などにも肖像写真が飾ってある。その遺体が安置されているホーチミン廟はハノイ一の名所でベトナム全国からベトナムの人々がお参りに来ている。わたしたちが行ったときも、晴れ着と思われる美しいアオザイを来た婦人たちのグループをいくつも見かけた。ホーチミン廟は外の入り口から廟の中までたくさんの軍人たちが警備していて、とても厳粛な雰囲気だった。
最後の日、もう一度旧市街を歩いた。あてもなく歩いていて、突然、赤い色がパッと目を引く通りに出た。よく見ると赤だけではないが、赤を主色に色とりどりのランタンが飾られている。ほかにも飾り物やおもちゃ、旗、子どもの仮装衣装、パーティーグッズのようなものが店先にあふれ、通りを埋め尽くしている。
何かと思ったら、祭事物通りというのだそうだ。もともと冠婚葬祭用の紙製品を生産する手工業の通りだったのが、現在は装飾品、特に祭りの季節ごとに変わるランタン、おもちゃ、飾り物などを売る華やかな商店街になったそう。
無数の色あざやかなものたち。でも素材は紙やプラスチック、化繊、針金など安価なものでできていて、お祭りが終わったら捨てられてしまう類のもの——。物は壊れる。どんなに大事にしていても壊れるし、なくすこともある。生物もおなじ。この世のすべてのものはそう。
祭事物通りに飾られ、あるいは落ちて踏みつぶされているものたちの風景を見て、その剥き出しの混沌ぶりに触れて、ふだん無意識のまま拘束されている窮屈な自我から少しだけ解放されたような気がした。蒸し暑く埃っぽい通りに目いっぱい氾濫しているそれらを見て、これがなんというか、わたしたちが生きている世界のミニチュアのように映ったのだ。
ランタン、紙細工の蝶、馬、星……。生はいろんなかたちでこの世にあらわれる。あらわれてはそれぞれの色を発し、持ち分の時間だけ存在し、消えていく。それぞれは全体から見たら泡沫のようなものだ。自分の生もそう。
だからそんなに背負って考えることもないという安堵のような感覚。同時に、こんな豊穣で混沌とした世界に生を授かり居合わせたんだという感慨のようなため息。十分ぐらいしかいなかったけど、そんなことを感じ、帰国後もなんとなく忘れられない印象を残した通りだった。
ふと、ハノイに行った。でも、ふとでも、ずいぶんいろんなものを受け取るものだ。
ハノイの人たちとは袖振り合う程度でしかなかったが、タクシーの運転手さんといい、ホテルの人たち、ガイドの青年といい、おおいに好感を持った。昔の日本人みたいに、ちょっとシャイだけど仕事はまじめ。でもそのあたたかくおおらかなホスピタリティーはマニュアルに仕込まれたものではなく、その人自身から来るものだったと思う。
たとえばガイドの青年は、わたしが彼の忠告を忘れて船の前方に行ったとき、本気で怒ってくれた。
ホテルのフロントの女性は、タクシー運転手がお釣りがないとき、自分のスマホのPayPayのようなものから代わりに払って精算してくれた。その人はまた、出発の日に頼んでおいた早朝タクシーが遅れたとき、謝ってくれたけど、過剰にではない。だれだって寝坊はする。飛行機に遅れないかちょっと心配にはなったものの、過剰に謝ったりしないおおらかな対応が悪くなかった。
ハノイ、ありがとう。たった四日間の滞在だったけど、忘れがたいものを受け取りました。
〜終わり〜
★最後までありがとうございました。ブログランキングに参加しています。よかったら応援クリックしていただけるとうれしいです。
![]()
にほんブログ村