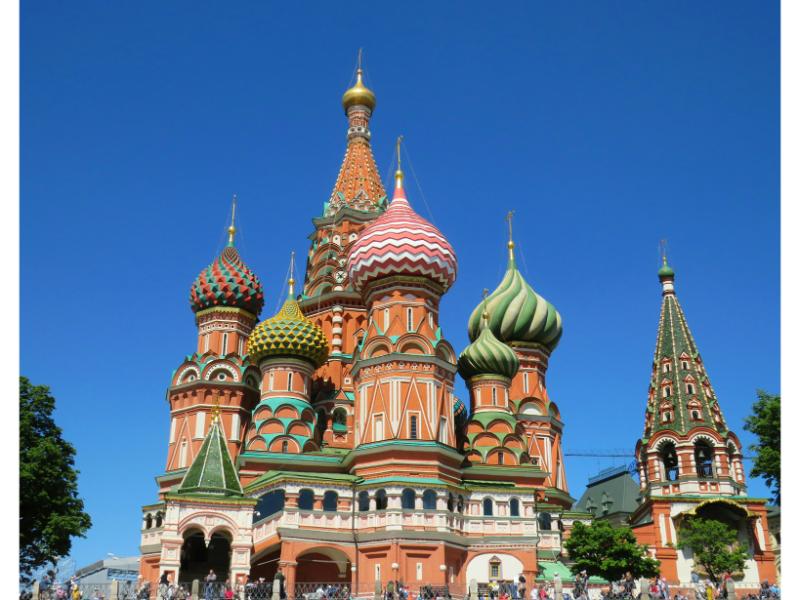「イリーナが、また、家出した」
フランス在住の友だち、ジャンヌから国際電話があった。
「また?」
おどろいて、ジャンヌに聞き返した。
イリーナも、ジャンヌも、ヴェネツィア大学でイタリア語講座を受講していたときの級友だ。1995年、結婚してヴェネツィアに移り住んだわたしは、週に二度ほど講座に通っていた。そこで仲良くなったのが、フランス人のジャンヌとイザベル、そしてロシア人のイリーナだ。
ジャンヌはだんなさんの赴任でフランスからイタリアにやってきた。四、五歳の子どもたちがいて、ヴェネツィア近郊の大学都市、パドヴァに家族で住んでいた。
イリーナはイタリア人と結婚していて、やはり四歳ぐらいの娘がいた。フリウリ州の地方都市から電車で一時間ぐらいかけ、講座に通ってきていた。ふたりともわたしより六、七歳年上で、当時三十六、七か。
一方、イザベルは若く、まだ二十代前半。フランスで大学生だったのが、旅行でおとずれたヴェネツィアで彼氏ができ、ヴェネツィアのムラーノ島でいっしょに暮らし始めたばかりだった。
わたしたちは週に二度、教室で顔を合わせると、そのあといっしょにお茶を飲んだり、町をぶらぶらして過ごした。わたしとイザベルは当時まだ仕事もなく、ひまだったが、ジャンヌとイリーナは幼い子どもをかかえて忙しかったはずだ。が、そのわりにはふたりとも、ヴェネツィアでずいぶんゆっくりしていった。クラスのある日はイタリア語の勉強を名目に、彼女たちが大手を振って子育てから解放される日だったのかもしれない。
ジャンヌは優秀で、英語、ドイツ語も堪能。イタリア語も、わざわざ語学講座など受けなくてもいいのでは、と思うほどよくできた。活発で人柄もよく、クラスのリーダー、おかあさん的存在で、わたしもイザベルもなにかと頼りにしていた。
イリーナはクラスのだれよりイタリア滞在歴が長く、イタリア語も上手だった。年はみんなより上だったけど、華のある美人で、ヴェネツィアの歴史や美術に関してはだれよりもくわしかった。気が向けば陽気で、おもしろいことをいってはみんなを笑わせる機知もある人だった。
四人でヴェネツィアをぶらぶらするとき、話すのはいつもイリーナだった。建築物を指差しては、バロックやゴシックといった時代とスタイルの差を教えてくれたり。ふつうのガイドブックには書いてないような、びっくりするような歴史的逸話を語ってくれたり。そんなときのイリーナは生き生きしていて魅力的な人だった。
が、その才気煥発さは、イタリアと、イタリア人の悪口をいう際にも遺憾なく発揮された。
イリーナはよくイタリア人の悪口を言った。
「イタリア人って文化度が低いよね。食べることしか考えてない。モスクワでは、夜は観劇やコンサートに行くわ。音楽や演劇を楽しむわ」
「イタリアの男って、なんでああサッカーの話ばかりなのかしら。女は女で服や子どもの話ばかり。うんざりだわ」
「わたしは劇場で仕事をしていたの。舞台衣装をつくる仕事よ。仲間はみんなアーティスティックな人たちで、常に刺激があった。でも、ここの人たちは平凡でつまらない。共通の話題がなにもなくて、退屈で死にそうよ」
住んでいる国の悪口を言うのは、まあ、在留外国人の常だが、それにしてもずいぶん一方的なイタリア攻撃、偏見そのものの悪口だ。ふだん鷹揚なジャンヌもさすがにあきれ、
「イリーナ、イタリア人だって観劇に行くし、アーティスティックな人はいるよ。今、田舎に住んで、主婦をやっているあなたには縁がないかもしれないけど……。ロシアだっておんなじでしょう?」
「さあ、知らない。田舎になんか住んだことないから」と、イリーナは取りつく島もない。
そのやりとりを皮肉な顔で聞いていたイザベルは、ふふんと意地悪く笑い、
「ロシアロシアって、そんなにロシアがよければ帰ればいいじゃない。ふつうの家にもバズーカ砲が置いてあるんだって?それぐらい、荒れてて、危険だそうね」
ソ連は1991年12月25日に崩壊している。その前後で、たくさんのロシア人が国を出た。イスラエル、ドイツ、フランス、イタリア、アメリカ——日本に行った人もいる。インフレや生活の苦しさ、明日に希望が持てないという絶望感から犯罪が増え、社会が荒廃していることは、当時ニュースで大きく報道されていた。(バズーカ砲に関しては真偽のほどはわからない。デマか、イザベルの誇張かもしれない)
しかし、当のイリーナはそれを聞いても、
「あら、そんなことないわ」と、どこ吹く風。
「そうかしら。ロシア人がいっぱい国外に逃げてるって、どのニュースも言ってるよ」
イザベルも攻撃の手をゆるめない。それでもイリーナは、
「知らない。少なくともわたしはちがうわ。わたしはパオロにどうしてもって請われてイタリアに来たのよ」
と、あくまで女王さま。
「そう、それはお気の毒だったわね」
イザベルはそう言うと、腹立たしげに席を立った。気まずくなり、その日のヴェネツィア散策はそこで解散となった。
同じ時期、イリーナの評判はクラスでも落ちていった。
イタリア語はもちろん、話もうまいし、美人だし、最初はみんなから一目置かれていたのが、常に自分が注目の的でなければ気が済まない、自分は話しても人の話は聞かない、それもいつも上から目線なことがわかってくると、みんなだんだんイリーナから距離を置くようになった。わたしもイザベルもそうだったが、それでもつきあっていたのは、ジャンヌがいたから。
ジャンヌは、同じ年ごろ、同じ子持ちという共通点からか、イリーナと親しくしていて、イリーナがクラスで孤立しても見捨てなかった。ジャンヌがみんなをつなぐボンドのような力を発揮していたおかげで、わたしも、イザベルも、イリーナとかろうじてつきあっていた。機嫌がいいときはおもしろい人だし、まだほかに友人もいなかったから、なんとなく惰性でくっついていた。
そんなある日、ジャンヌがイリーナの誕生日会をしようと言い出した。イザベルとわたしはそんなに乗り気でもなかったが、なにせそのころはひまだったので、ジャンヌが言うならと、サンマルコ広場に近く、アクセスのいいわたしの家に、お昼に集まることになった。
ジャンヌはキッシュロレーヌとバラの花束、イザベルはケーキとワインを持ってきた。わたしはローストチキンを焼き、テーブルセッティングをして出迎えた。
しかし、約束の一時を過ぎても、肝心のイリーナが来ない。半時間すぎ、一時間過ぎ、イリーナの自宅に電話してみるが、だれも出ない。当時は携帯電話がまだ一般的に普及しておらず、ほかに連絡のつけようもなかった。
わたしたち三人は心配と空腹で話もはずまない。だんだん疲れてきて、プレゼントのバラの花束も、心なしか萎れて見える。
イザベルのおなかがぐうと鳴った。しかたない、先に食べようということになったが、料理をあたためなおす気にもなれず、さめたチキンが味気ない。
食事が終わり、イザベルが、「ケーキ、どうする?」と言った。
『イリーナ、誕生日おめでとう』と書かれたプレートが乗ったケーキに、みんなの力ない視線が集まる。そこにリリリと電話が鳴った。急ぎ受話器を取ると、イリーナだ。
「ごめんごめん、ちょっと遅れちゃった。これから行くわ」
これからって……もう四時だ。どっと疲れ、わたしは無言で受話器をジャンヌに渡した。
ジャンヌはおだやかな口調で、しかしきびしい表情で、イリーナと話している。受話器を置いたジャンヌは、わたしとイザベルを見て、
「家でなにかあったそうで、出られなかったらしいの」
「だからって、電話で一報ぐらいできたわよね」
色めき立つイザベルとわたし。
「そうね。今日はもう終わりって伝えたわ」
「今日は、じゃないよ。あの人とはこれで終わり。もう金輪際かかわりたくない」とイザベルが怒声をあげた。
ジャンヌはため息をつき、主人公のいないお誕生日会はそれでおひらきになった。
その次の週、クラスで顔を合わせたイリーナは、昼食会をすっぽかしたことなどまるでなかったかのように、陽気に声をかけてきた。ひとことの謝罪もない。
頭に来て、ジャンヌに、なぜあんな人をかばうのか聞いてみた。ジャンヌは空を仰いでため息をつき、
「しょうがないひとだけど、ロシアの悩める、さまよう魂なのよ。あぶなっかしくて見てられなくて……」
イザベルとわたしは思わず顔を見合わせた。ジャンヌの寛大さはもはや人間の域を超えている——。
イザベルはジャンヌに、Santa Jeanne della Misericordia「慈悲深き聖ジャンヌ」とあだ名をつけた。わたしはそれを日本風に「ほとけのジャンヌ」と変えて呼んだ。イリーナがとんでもなく自分勝手な一方、ジャンヌは果てしなく寛大だ。
しかし、どんなにジャンヌがかばっても、わたしとイザベルの心がイリーナから離れていくのを止めることはできなかった。「ロシアの悩める、さまよう魂」なんて言われてもよくわからなかったし、まだ若かったわたしとイザベルには、イリーナみたいなめんどくさいおばさんは、もう、どうでもよかった。イタリア語講座は終了し、クラスに通うこともなくなった。ほかでもだんだん友だちができ、イリーナとジャンヌとも自然に遠のいていった。
「イリーナが家出した」
ジャンヌから電話があったのは、その約一年後だった。唐突な「家出」ということばにわたしが動揺していると、受話器の向こうで、ジャンヌが焦った口調で、
「心あたり、ないよね?」
と問い詰める。わたしに心あたりがあるわけない。
「だんなさんのパオロから電話があったの。帰ってきたらメモが置いてあって、ちょっと出かけてくるって。でも昨夜は帰らず、今日もまだ帰ってないって——」
「!!……娘さんは、ソーニャちゃんは?」
「ソーニャは大丈夫、パオロといっしょにいる」
「どうしたんだろう……心配だね」
「うん……。パオロもさっき警察に届けたらしいけど、まだなんの知らせもないの。もしイリーナから連絡があったらすぐ知らせてね」
「もちろん」
不安な気持ちで受話器を切った。いったいどうしたんだろう。まだ四歳の子どもを置いて突然いなくなってしまうなんて、いくらイリーナでも度が過ぎる。事故や事件に巻き込まれてなければいいが……。
その日は気になって、結局なにも手につかなかった。
翌日の昼ごろ、電話が鳴った。もしやと思い、急いで出ると、
「イリーナが帰ってきた」
と、ジャンヌの声が聞こえた。
「無事なの?どこにいたの?」
「無事だから安心して」
ほっと安堵の息をつき、どっと脱力した。
「で、どこにいたの?なにしてたの?」
「ミラノにオペラを観に行ってたんだって」
「ミラノ?オペラ?」
「うん。どうしても見たくて飛び出しちゃったんだって」
「……」
「ニコニコ上機嫌で帰ってきて、素知らぬ顔でソーニャちゃんを幼稚園に迎えに行ったらしい」
「ニコニコ……」
「まあ、無事でよかった」
「無事でよかったって——まったく人騒がせな人ね。ジャンヌ、イリーナがいなくなったって、次回からは電話なんかしてこないでよ。いい迷惑だわ」
「……」
受話器の向こうでジャンヌの重いため息が聞こえたが、わたしは電話を切った。ひと晩じゅう心配させられたのに、謝罪のことばのひとつもない。イリーナなんかどうなったって、もう知るもんか。
その後、イリーナに会うことはなかった。ジャンヌはその三年ほどのち、一家でフランスに帰った。イザベルは婚約者と結婚してムラーノ島に残り、わたしは離婚して日本に帰国した。こうしてかつての四人組は地理的にもみごとにバラバラになった。
「イリーナがまた家出した」
フランスにいるジャンヌから日本にいるわたしに国際電話があったのは、帰国して二年目、今から十六年ほど前だ。
国際電話は二回目で、最初は帰国してすぐのころ。幼い娘を連れて日本に帰ったわたしを心配して、わざわざフランスから電話をくれた。なんとか元気でやっている、娘も東京の小学校に慣れてきたと伝えると、とてもよろこんでくれた。
今回の電話は二度目。国際電話がべらぼうに高かった昔とちがい、そのころはスカイプやら、安いテレフォンカードができて、海外からでも気軽にかけられるようになっていた。
「また?」
わたしは久しぶりに、イリーナの、あの華のある笑顔を思い出した。あれから十余年。イリーナももう五十を超えただろう。
「娘さんはどうしたの?大丈夫なの_」
イリーナにはソーニャというひとり娘がいて、かわいがっていた。さすがにもう幼な子ではないが、それでもまだ十六、七のはず。突然母親がいなくなって、少女はどうしているのか。
「ソーニャは大丈夫。パオロがついてるから」
前と同じセリフをまた聞いた。パオロはイリーナのだんなさんだ。技術者で、仕事でロシアによく出張していた。そこでイリーナと出会った。
ジャンヌはつづける。
「イリーナはあのあとも何度も家出をくりかえしていたの。そのたびにパオロから電話がかかってきて、心配するんだけど、二、三日するとけろっと帰ってくるのね。それでパオロもソーニャも、もう慣れっこになっていたんだけど……」
あきれた。そうだったのか。イリーナの家出はあのあともずっとつづいていたのだ。
「それが今回は長かったの。一週間ぐらい経って、みんなほんとうに心配しだした。事故にでも遭ったんじゃないかって。それでわたしも心配していたんだけど……。そしたら、どうしたと思う?」
「え、わからない。どうしたの?」
「うちにひょっこり現れたの。南仏の、エクサンプロヴァンスの我が家までやってきたのよ」
「えー!突然?」
「そう。たまたまわたしたちが在宅していたからよかったけど、ヴァカンスで留守にしてたらどうするつもりだったのかしら。イタリアから電車を乗り継いできたって言ってた……」
「……。元気だったの?」
「いや、それがそうでもなくて……。着いたときは疲れきった様子で、迷子みたいな顔で泣きべそかいてた。胸が痛んだわ。うちでお風呂入ったり、ごはん食べたりするうち、元気をとりもどしていったけど、さすがに昔ほどの向こうっ気の強さはなかったわね。」
「……。イリーナはジャンヌに会いに来たの?」
「さあ、どうだろう。彼女はロシア人。ロシア人って悩める、さまよう魂の持ち主でしょ? またぞろ彷徨したくなったんじゃない?」
ジャンヌのなつかしい「ロシア人は悩める、さまよう魂」説を、久しぶりにまた聞いた。彼女はこの自説で常にイリーナをかばってきた。
「うちには一週間ぐらいいたかな。気分が沈んだりすることもあったけど、最後は元気で帰っていった。心配だから飛行機に乗せたわ」
イリーナも変わらないけど、ほとけのジャンヌも健在だ。
イリーナのほかにロシア人の知り合いなどいないわたしには、ロシア人が「悩める、さまよう魂の持ち主」なのかどうかわからない。ジャンヌがロシア文学を読んで、勝手にそう言っているだけなんじゃないかと思っていた。イリーナに会ったころ、自分はまだ若く、世界もせまかった。ロシアに興味もなかったし、イリーナのことも、ただ面倒な人としか思えず、彼女のことを理解しようという気もなかった。
しかし、それから一年後、ひとりのロシア人と短い会話を交わした。それがきっかけで、長い年月忘れていたイリーナのことを思い出すことになる。
彼の名はセルゲイ。アメリカ、ロサンゼルスのタクシーの運転手さん。
旅先でたまたま彼のタクシーに乗って、世間話がはずんだ。年はわたしと同じぐらいか。ロシア人だという。バックミラーから見える顔は、青い目、金髪の、なかなかの美男だ。
ロサンゼルスの生活ってどんな感じ?と聞くと、自分は郊外に住んでるけど、それでも生活費は高いし、治安はよくないし、子どもたちの学校への送り迎えが大変だと苦笑した。アメリカ人の妻とのあいだに、ふたりの子どもがいるそうだ。
わたしは彼に、どうしてアメリカにやってきたのかを聞いた。
「どうして?ソ連崩壊時にやってきたんだよ」
決まっているでしょ、という感じの口ぶりだった。ああ、そうか。彼もその世代のひとりだったのか。
「聞いてるでしょう?あのころのロシアは絶望的な状況だった。ストレスからアルコール中毒になったり、自殺した人も多い。自分は生き延びたかったから国を出た」
「……」
「でも、あのまま滅びるかと思われた祖国は、意外にも再生した。あのとき国に残ってその後の発展の波に乗り、成功した友人もいる。自分は風向きを読み間違えたんだって思ったよ。学位も取って、これからって時だったのにね」
「今はこの国に家族ができて、まあまあ平和で、悪い暮らしじゃない。でも、自分はタクシー運転手。それがまだ信じられないんだ。ずっと教師になるって思ってたからね……」
「どこで、どうなっちゃったのかな。何度考えてもわからないんだ。でも、まあ、しかたない。こうなった。Wrong time wrong placeって言うでしょ?あれだよ」
セルゲイは乾いた声で笑った。バックミラーに映る彼の、青い、遠い目。さらにその向こうには、フロントガラスを通して、カリフォルニアの青い空がどこまでもつづいている。
セルゲイの話を聞いてはじめて、国が滅びるというのはそういうことなんだ、と、肌身を持って感じた。日本で平和と繁栄を享受してきた世代のわたしは、それまで戦争のニュースを見ても、それが個人の人生にどんな影響を及ぼすか、なかなか想像がおよばなかった。どこか対岸の火事だった。
しかし自分も、日本からイタリア、イタリアから日本へ移住し、そのたび職業を変える経験を経て、アイデンティティーが揺らぐ経験をした。自分がどこの何者なのか、ときどきわからなくなる。だからなのか、セルゲイの話は心に沁みた。
そして、イリーナのことを思い出した。
イリーナは夫のパオロに請われ、しかたなくイタリアに来たと言っていた。だけど、ほんとうにそうだったのだろうか。イリーナもまた、故国崩壊の混乱のなか、海外移住に道を見出した人だったかもしれない。
イリーナはいつもモスクワでの華麗な暮らしを自慢していた。が、ひょっとしたらそれは彼女の想像の産物だったかもしれない。故国を去った痛み、昨日までの暮らしを手放した苦しみから逃れるため、時に虚言をまき散らし、自分を守っていたのかも。
イタリアの片田舎での暮らしを軽蔑していたイリーナ。人と話すときはいつも上から目線だったイリーナ。約束をすっぽかし、家出をくりかえし、それでも女王然とふるまっていたイリーナ……。
Wrong time wrong place. どんなに優秀でも、どんなに努力をしても、間が悪いときに間が悪い場所にいたら、思うとおりにはいかない。ひとが幸福に生きるには、幸運もやはり必要だ。でも、運は自分で選べない。
自分は戦後の平和な日本に生まれ育った。自分が享受しているものは、平和な国に生まれた幸運によるところが大きい。しかし、まるであたりまえのように受け取ってきたこれらの幸運が、これからもつづく保証はどこにもない。むしろ、世界はふたたび、きな臭くなってきている。
イリーナの痛み。もうどこにも存在しない、かつての故郷とそこでの暮らしへの望郷の念。
セルゲイの苦い後悔。生き延びようと母国を去ったものの、ロシアはその後、再生した。残った連中は、今、羽振り良くやっている。自分は選択をあやまったのかもしれない……。
そして、今、国を追われているガザの、ウクライナの人たち。シリア、アフガニスタン、ミャンマーほか、戦火に追われたり、内戦があったり、独裁政治に弾圧され、自国を去ることを余儀なくされた人たち——。
今この瞬間、いったい何十万、何百万の人たちが、Wrong time wrong placeとつぶやいているのか。できごとは自分の都合とはまったく関係なく起こり、人を巻き込んでいく。どんなに計画しても、どんなに努力しても、神さまのサイコロひとつで、運命はころっと変わってしまう。
イリーナの家出癖はしかし、あのエクサンプロヴァンス以来、おさまったそうだ。ジャンヌのようなあたたかい人、ほら話とわかっていても笑って聞いてくれる、突然訪ねてきてもだまって受けとめてくれる、そんな友だちの存在が、イリーナを落ち着かせたのか。それとも単に、彼女も年を取り、家出する元気もなくなったのか——。
最近、ジャンヌと話したところ、イリーナの娘さんは結婚した。イリーナはモスクワに残ったおかあさんの介護のため、ちょくちょくロシアに帰っているそうだ。
イリーナの、さまよう、悩める魂は、長い年月をかけて、少しは安らぎを得ただろうか。どうかそうでありますように——。
イリーナの心の平安を、遠い空の下から、心から、祈る。
★最後までありがとうございました。ブログランキングに参加しています。下の「イタリア語」というアイコンをクリックして応援していただけるとうれしいです。
![]()
にほんブログ村
UnsplashのAnastasiya Romanovaが撮影した写真, Thank you!