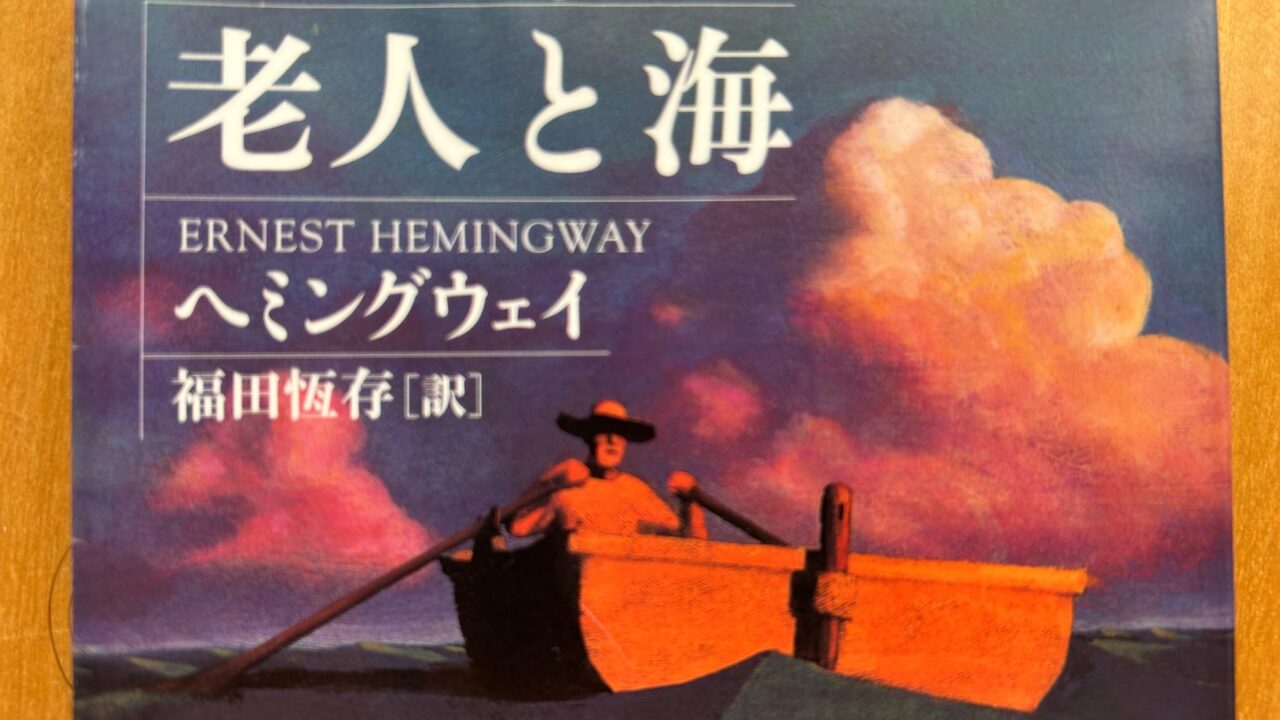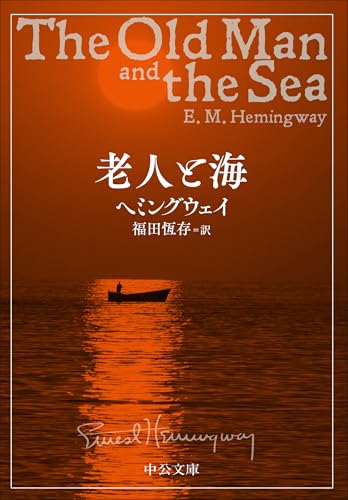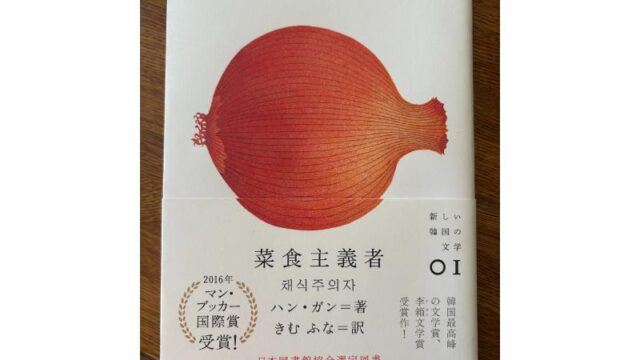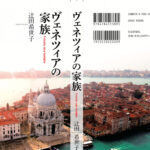何十年ぶりにヘミングウェイの「老人と海」を読んだ。中学だか高校のころに読んだ記憶があるが、あまり印象に残らなかった。それがちょっとしたきっかけでこのたび再び手に取った。
キューバの老漁夫がたったひとりで大海に漕ぎ出し、巨大な魚を相手に三日三晩死闘をつづける物語。今回は暑さも忘れいっきに読んだ。すばらしかった。
本にも出会いのタイミングというものがあるのだろう。学生の時分にはそのよさはわからなかった。老人にも釣りにも興味が持てず、物語についていけなかった。それが今回ぐいぐいと引き込まれるように読めたのは、年齢が主人公に近づき、人生経験を積んだからかな。年をとったこと以外はなんの共通点もないにかかわらず、まるで自分のことのように心に響いた。
物語は「かれは年をとっていた」という冒頭から始まる。主人公である老漁夫はすでに多くのものをなくしている。妻にはとっくの昔に先立たれ、粗末な小屋にひとり暮らし。体力も衰えた。漁夫としての腕が唯一残ったものだったのに、このところ八十四日も一匹も釣れず、運にまで見放されてきている。
でも老人はあきらめない。まだ手はあるさと恬淡としている。八十五日目の今日こそでかい獲物を仕留めようと、オンボロ小舟を出す。ひとり船を漕ぎ、メキシコ湾から沖へと出ていく。
老人は海鳥たちの動きから海中の魚の動きを読む。釣綱を海にたぐらせ、獲物がかかるのを待つ。満点の星の下、いろんなことに思いを馳せる。
昔、水夫としてアフリカに行き、ライオンを見た。海亀をとった。腕相撲で強敵を打ち負かした。野球はディマジオのファンだ。今夜の試合はどんな調子かな?
そうこうしているうちに手ごたえがあった。大物のようだ。老人は魚を引き寄せようとするが、魚はそれをゆるさない。悠々と泳ぎ、老人の船を沖へ、さらに沖へと引っ張っていく。
老人は魚に曳かれながら相手の出方を探る。しかし何時間たっても魚は姿をあらわさない。
老人は綱の動きを見逃さぬよう気をつけながら、眠り、食べようとする。が、ひとりなのでむずかしい。
「ああ、あの子がいたらなあ」
老人はつぶやく。あの子というのは小さいころからかわいがり、釣りを教えてきた愛弟子の少年だ。老人を慕い敬っており、最高の相棒なのだが、親に反対され今回の漁には連れてこれなかった。
疲労が増してくる。左手がつり、硬直して動かない。なにか食べないとからだが持たない。水もそろそろ尽きてきた。
突然、魚が跳ねて姿をあらわした。小舟より2フィートも長い、想像を絶する巨大なカジキマグロだ。
長い睨み合いの時間が終わり、老人と魚の死闘がはじまった。老人はありったけの力をふりしぼって巨魚とたたかう。時に失神しそうになり、そのたび「頭よ、しゃんとしろ」と言い聞かせてまた立ち向かう。
巨魚も必死だ。なんとか逃げようと七転八倒し、そのたびに小舟がひっくり返りそうになる。老人も背中や手を怪我する。
「ああ、あの子がいたらなあ」老人はまたもやつぶやく。航海中、何度も何度もつぶやく。それが哀切だ。
しかしもちろんあの子はいない。だれもいない大海で老人はたったひとり、巨魚とたたかわねばならない。
三日三晩にわたる死闘の末、とうとう老人は巨魚に勝った。が、帰途、勝利の獲物にサメの群れが襲いかかり……。
ラストは苦い。が、暗くはない。
厳しさの、孤独のなかに無数のきらめきがある。老人の「あの子」への愛。かれを慕い、あれこれ世話を焼く少年のやさしさ。船のまわりを跳ねるトビウオや鳥に心を寄せるあたたかいまなざし。そして巨魚の威厳ある静かで誇り高い抵抗……。
たとえ生きることが不条理で、個人はそれに対しなすすべがないとしても、そのたたかいを投げずにつづける老人の姿に勇気づけられる。
あの子はいないしサメは襲ってくる。それでも大海でひとり、小舟をこがなければならない——老人じゃなくても、だれにとっても、生きるとはおそらくそういうことなのではないか。
老人が決して悲愴でなく、常に飄々と明るいのにも救われる。運に見放されても、どんなピンチのときでも、まだ手はあるさとあきらめない。ボロボロになっても最後まで自らの目的を見失わず、勝負を完遂する。
この作品はヘミングウェイにとっても会心の出来だったようだ。1940年の「誰がために鐘は鳴る」以来十年の沈黙、その後に発表した「河を渡って木立の中へ」も不評で、ヘミングウェイはもうダメだと言われ、気鬱におちいった。長いあいだ苦しんだが、最後にこの作品を書き上げた。当作品を掲載したライフ誌は「老いたるヘミングウェイが傑作を書き、チャンピオンシップを奪還した」と書いた。老人と文豪の姿が重なる。
この先、自分も老いにあがき、いろんなものを失っていくのだろうが、希望を失いそうになったらまた読み返したいと思った。最後まで小舟をこぎつづけられるように……。
★最後までありがとうございました。ブログランキングに参加しています。よかったら応援クリックしていただけるとうれしいです。
![]()
にほんブログ村